挿絵・文:来栖ぴよさん!Special Thanks!
表紙絵:ピンクのでめ金
| ネメシスを追う者 その気がなくて嫌がっているのなら普通だが、その気があるのに嫌がっているように見えるのは、彼女の長所だと思う。何をされるかわかっているくせに戸惑いの表情で見上げて疑問符を浮かべているように見せるのだ。性的なこととは一切関係を持たずに生きてきた聖女のようで、こんな時ですら未だに童女のようで、実際に処女であることは疑いないのだが、それでも誘ったのは彼女だ。 『誘った』という言い方は少々不適切かもしれない。『申し出た』とでも言うべきか。それほど彼女の言い方と態度は固かったが、結局のところ言い回しがどうであれ提示した内容に差異はない。 ベッドに沈んだ細身の身体に覆いかぶさって軽く首筋を舐め上げると、リザがびくりと震えてロイの肩に手を添えた。その手は引き寄せようとしているわけではないらしいが、押しのけて抵抗しようとしているとも思えない。本当にただ当てられただけの繊細で壊れそうな手をとって、ロイは白い指に自らの指を絡めた。 「マ…スタングさん…? なに…をっ」 何を、と尋かれて懇切丁寧に口で説明するよりは身体に教えたほうが早い。リザが言葉を紡いでいる途中にそれを無理やり塞いだ。リザは硬直している。緊張しているのか。 「口、開けて」 「…え?」 疑問を上げる声と共に半開きになった薄桃色の唇に再び口づけを落とす。掬い取った舌は今までキスをしたどの女性のものよりも小さくて何だかおかしな気分になった。だが、悪い気はしない。リザの舌を蹂躙するたびに握り締めた指がびくびくと痙攣する。彼女は舌にこれほどの感覚が集中しているなんて考えたこともなかったのだろう。それは異性によって初めて思い知らされる。 苦しかったのか喉で声を出したリザから名残惜しく離れた。薄桃色だった唇は赤く濡れそぼり、薄く開いたそれから湿った吐息が漏れていた。彼女が望むか望まないかに関わらず十分に扇情的な光景である。ベージュのシーツの上で漆黒の喪服に包まれたビスクの肌が薄闇でくっきりと浮かび上がるように映えている。まるで曝されるのを待っているかのように見えた。既に上着は着ていない。彼女が自分で脱いだからだ。 ワンピースを脱がそうと背に手を入れると、リザは進んでひじを突いて起き上がり自分でファスナーを下ろそうとした。嫌がる彼女を強引に征服する様を想像して愉しんだ事がないわけではないが、やはり誰よりも大事な少女なのだ。合意の上であることが最も望ましい。いや、震えながらも従順にファスナーを下ろそうとする彼女を黙って視姦して愉しんでいるのだから、趣味が悪いことには変わりないか。 緊張した手は先端をうまく掴む事ができず、焦ってますます不器用な動きを見せている。これ以上放っておくのも酷だ。それに自分はそう気の長いほうではない。 薄い腰に両手をあてて引き寄せ、座した自分の脚に閉じ込める。こつんと額をリザの額にあわせて微笑むと、安心したようにリザの手の力が抜けた。その手を解いてロイの手が代わりにファスナーを最後まで下ろした。フックを外し、合わせを掴んで肩まで持ってくるとリザが小さく声を上げた。 「あ…」 「怖気づいたか?」 いえ、とリザは首を振って、消え入るような声でごめんなさいと謝った。 「イイエ、気にしてないよ」 再び仰向けにベッドに押し付けると、不安そうな瞳が見上げる。 「あの…マスタングさ…っ」 普段は必要なこと以外殆ど喋らないくせにこんな時だけ妙に口を開きたがる。塞いで欲しいのか? 期待に応え、口を塞いだまま肩まで持ってきたワンピースと下着のストラップを同時に下ろして、露になった胸に指を這わせる。美味いものもろくに食べられないような家庭環境で育ったとは思えないほど、しっとりと柔らかく手に吸い付いてくるそれは下着のせいではなく本当にふくよかだった。筋肉も脂肪もついていないまだ子供のような身体つきをしているくせに、男を魅惑する準備だけは整っているようで、例に漏れず虜にされながらも、何か少々癪に障るものを感じた。胸の飾りに人差し指をあてて揉みしだくとしこりが残っていて、この大きさでまだ未成熟であることがわかる。年齢的にも当然のことではあるが、清純な彼女の性質と身体的特徴が間逆なのはリザにとって悲劇かもしれない。 露になった膨らみの感触に夢中になっていたせいで気がつかなかったが、いつの間にか首を振って唇をかわそうとする彼女の頭を捕らえて口内を犯し、明らかに抵抗の意を示してロイの肩を押し付ける両手を無視して、柔らかな感触と硬くなっていく突起の感触に酔いしれていた。意外にもこれでは当初の望みどおり、合意なし状態だ。 一旦止めてリザの顔の横に両手をつき、身体を上げた。遠慮なく体重をかけていたが、やはり壊れそうに細い。苦しかったのだろうか。初めて桃色の突起が視界に入って、ふと目を逸らした。その先には泣きそうなリザの顔があった。 「やめてください…違…うんです…」 「違う? 何が?」 「私…は、そんなつもりじゃ…」 リザが顔を背けると父親が亡くなって泣き腫らしたばかりの目から更に涙が奪われて、潤んでいた瞳から終に一粒涙が零れた。ロイの胸板に押し付けられていた手がそろそろと外され、露になった胸を隠すように自分自身を抱きしめる。 そんなつもりではなかった? 自分で脱いでおいて。彼女が何を言っているのか理解できない。 「それは、今更というものだよリザ」 自分のどこにこれほどの支配欲が隠れていたのだろうかと思う。人よりは好色だという自覚はあったが、これほどの執着を見せたことなどただの一度もなかったはずだ。絶望に見開かれた目と言葉を紡げずに微かに動く唇が、今までのどの女の所作よりもこれほどまでにそそるなど、思いもしなかった。 「私…は、…ただ…」 「やめて欲しい?」 マリオネットのようにぎこちなく、リザの首が縦に動いた。 「嫌だと言ったら?」 答える代わりに、リザの目からまた一粒涙が零れた。ブラウンの瞳はロイから逸らされ、諦めたようにただ暗渠だけを映していた。君が嫌ならやめる、そう言うつもりだったのだ。しかしどうしてもその言葉が口から出ない。反対にその唇は先ほど弄っていた桃色の蕾を求めていた。突いていた手はリザの脚を折り曲げ、膝下のスカートの丈から滑らかにストッキングを辿って腰まで手繰り上げる。 「や…」 爪を引っ掛けた箇所から伝染していく音を間近で聴きながら、破れたストッキングの穴から覗く雪のように白い内腿に舌を這わせた。 「い…や…嫌…や…だっ…」 リザの口から零れる甲高い小さな声に快感は一欠けらも含まれておらず、そこにはただ恥ずかしい体勢でストッキング越しに舐められる嫌悪感しかない。 「悪いが、…いい思い出にはしてやれそうもない」 真っ白だった穴はロイが唇を離すときにはもう鬱血して赤く染まっていた。 「…ぁ…」 下着ごとストッキングを引き下ろされ、リザは毛皮を刈られた子羊のように頼りなく震えた。 何度も、何度もやめようと思ったのだ。彼女が嫌と言う度に、痛いと言う度に、哀れなほどがくがくと震える膝が目に入る度に、それでも苦痛からくの字型に曲がってシーツを歪ませるその細く白い指ですら、眩暈を起こすほど美しいフォルムをしていて、小さくあがる悲鳴だけでぞくぞくと快感が背筋を走り、リザを組み敷いているという事実を認識するだけでも果ててしまうほどで、良心と慙愧の念を凌駕し続けるだけの衝動を抑えることができなかった。 彼女が感じる痛みには到底及ばないとわかっているが、ロイの胸もずっと締め付けられるように痛んでいた。 ここまで、彼女を傷つけてまで、する必要があったのか。 彼女が嫌と言った時点でやめるべきではなかったのか。 こんな年下の少女相手に。 保身を侵してまで。 本気になるわけがないのに。 元はと言えば。 そう、そうだ。 「君が、…誘うから、だ」 ぽつりとつぶやいた言葉は闇に飲み込まれて消えたように思えた。だるいのか痛いのかリザがぐったりと動かないせいだ。傷ついたリザに責任を転嫁する自分があまりに勝手で腹が立つ。嫌われただろうなと思うと胸の痛みがいっそうひどくなった。 当たり前だ。一生許してはもらえないかもしれない。ああ、こんなはずではなかったのだ。父親代わりに守っていこうと心に決めたのに、どこで道を間違えたのだろうと考えれば、やはり、あの時だ。 葬式の後始末で泊り込むことになり、夜半まで作業をしているところを寝室に呼ばれた。まだ喪服のままでいたリザに驚きを隠せなかったが、彼女は電気もつけずに言った。 『やはり、貴方に差し上げようと思うのです』 ぱさりと脱いだ上着が床に落ちる。 それはロイの理性が砕け散る音と同時だったのかもしれない。 そして、我に返った今、ただ胸の痛みだけが残った。 誘ったリザが悪いと言って片付けるのは簡単だ。 でも、それでは駄目なのだ。 「リザ…」 睫毛が濃く陰影を落とした伏せ目がちな瞳がだるそうにこちらに向けられた。 「リザ」 謝らなければ。 躊躇していると、吸い込まれるようにすっと目蓋が閉じられた。 「リザ…!」 「…マスタング…さん」 掠れた声がゆっくりとこぼれ出る。 「どうして…?」 ずきんとこれ以上ないほどに胸が痛んだ。 だがその瞬間、ふ、と。 幻覚だろうかと思ったが。 確かに、ふと目を閉じたままのリザの頬が緩んだ。 「どうしてここまでして気付かないんですか…貴方は…」 呆れた様に、穏やかに流れるその声に、ロイが予測していたような怒りと軽蔑は含まれていなかった。 顔を顰めながらリザが緩慢な動作で身体を起こした。痛むのだろう。どろどろに汚れた身体をゆっくりと反転させる。 「もう…私は、これを差し上げると言ったのですよ…?」 振り返った顔は明らかに苦痛と疲労を滲ませていたが、それでもロイが見たことがないほど、リザは優しく微笑んでいた。 「あ…」 眼前に晒されたものと、とんでもない勘違いと、優しすぎるリザに対する驚きで、ロイはしばらく指一本動かすことができなかった。 「ああ…」 「…わかりましたか?」 美しい。そして、なんて愛しいのだろう。 背中に彫られた錬成陣についてではなく、リザの存在自体について、単純にそう思った。 「じゃあ…やっぱり…」 「え?」 「ダ…ダメ、…だったのか…?」 滝のように汗を流すロイをちらりと横目で見て、リザは拗ねたように頬を膨らませた横顔を枕にうずめて、はい、と言った。 「…すまん」 「はい」 「ごめん…」 「そうですね」 「ごめんなさい…」 「ええ」 誘われたからなんて自分の言い訳に過ぎなかった。自分の欲望で一生恨まれても仕方がないようなことをした。何度謝っても赦されるようなものではない。でもいつの間にか返事をするリザの口元が緩んでいることを、ロイは気付いていた。 背を向けるリザを後ろから抱きしめて、首筋に顔をうずめた。 「…マスタングさん…」 「ちゃんと言ってくれれば良かったのに」 「何度も、言おうとしました…」 「キスしても抵抗しなかったじゃないか」 「だって…! 背中を見るだけなのに、どうして…するのかと思って…びっくりして…」 思い返せば確かにリザは戸惑っていた。 「そうか、すまない」 今度はちゃんと断って、ロイは悪びれる様子もなくリザの下肢にぬめる指を滑らせた。 「っ…」 「もう一回」 今度は許してもらえないかもしれない、とは思っていなかった。ロイはリザが無条件に何もかも許していることを学んでしまったのだ。 抗議しようと開かれたリザの唇を塞いでも、もう胸は痛まなかった。 その日からしばらく、ロイは自宅にこもって写し取った錬成陣の研究に没頭していた。 |
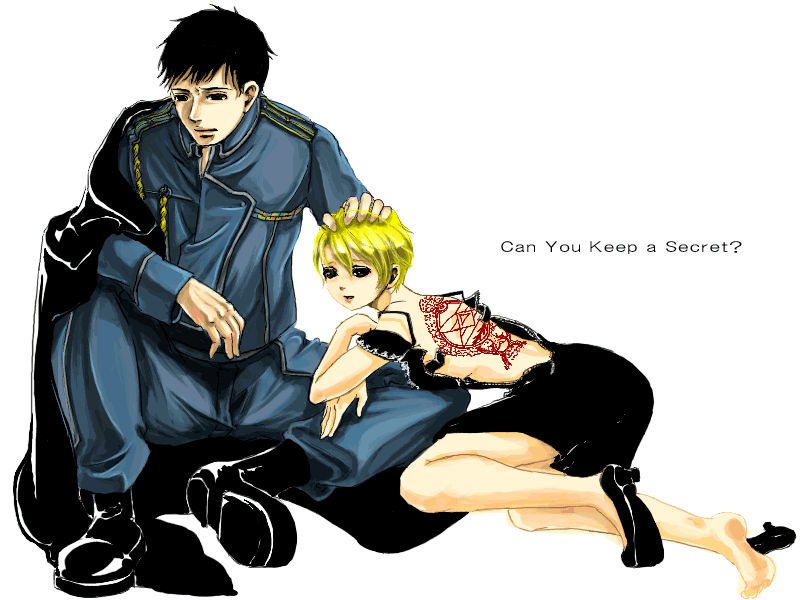
|